内職の歴史・昔から現在
内職の歴史は非常に古く江戸時代から存在したと伝えられています。
元々は農家のお嫁さんなどが(出産や病気などで)キツイ畑仕事などが出来ない時に、納屋で(わらじ)や(簑みの)などを作るために手作業や手加工などで軽作業を行い出来高に応じてご近所の方と物々交換などでお米や金品を受け取とっていたのが内職の起源と言われてます。
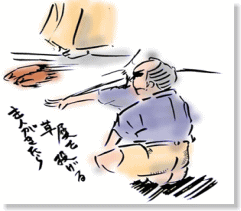 人間はいつの時代も仕事をして対価を得て食糧などを調達してきたという歴史がありります。
人間はいつの時代も仕事をして対価を得て食糧などを調達してきたという歴史がありります。江戸時代頃から農民が農業の傍ら内職をする時代がやって来ました。当時でも原料や器具さえあれば農村でも副業的に仕事をする事ができました。
色々な機法が伝来した江戸17世紀初め頃にも民家で金欄・緞子・縮緬などの高級絹織物も織機で織られていました。
昔の人は色々な技法を学び、いずれ、問屋商人が生産者に資金や原料や機械を前貸しして生産を行わせるようになりました。
問屋商人はその製品を買い上げて街で販売するという生産形態が時代とともに発達していきました。
当時では家内工業といいまして農民は自給自足の農業経済から家内工業に本格的に転職する人もいました。
19世紀になると、間屋制家内工業の生産性に可能性を感じた問屋商人が工場などを建設していきました。
それに伴い仕事内容は、それぞれ、専門性に分かれて分担されていきます。【これを手工業的分業といいます】
江戸時代中期の1780年代では関東の桐生や足利などの民間絹織物業者で10台以上の質の高い織機を設置して常時10人以上の奉公人を本格的に雇って生産性と合理性を求めた工場制手工業者が多数存在していた事が確認できます。
それと同時に問屋さんが荷車を引いて回れる距離であれば盛んに家内工業も発生していた事が想像できます。しかし、まだ電話などもない時代で契約農家によっては病気で数日寝ていたり材料がなくなったなど敏速な連絡ができない、また織機などの機械が故障して仕事を中断してしまった事が考えられます。
限界を感じた問屋制家内工業の経営者はこの問題を解決するために工場を建て奉公人を工場に集め材料・原料・機械を一括管理する画期的な手法・方法を考え出しました。
歴史から見ましても、(商人)工場制手工業者と(農民)家内手工業が共に発展してきたことがうかがえます。 そして明治・大正・昭和と時代は移り発展し世の中の仕事がある程度増えてくると、昭和20年あたりでは内職はお年寄り専門の仕事となりました。
病気で働きに行けないお年寄りなどが空き時間に軽作業をすると同時に内職は貧しい人がする仕事というイメージが定着してきました。
しかし、戦後昭和30年代以降、高度経済成長になりますと、急激に20代の女性、内職さんを希望する人が増えました。
手土産品の加工・袋詰め・あて名書き・機械部品の検査・小物その他・軽作業など。
内職さんが増えた理由として終戦後から徐々に子どもを出産する女性が増えた影響で4人兄弟・5人兄弟があたりまえの時代になりましたので仕事と子育てを自宅で両立する必要がでてきました。
当時の内職さんは、旦那さまが出勤したあとに、一日あたりの時間6~8時間頑張って内職収入を生活の足しにしていたようです。
平成にはいってからは以前より生活レベルが上がった影響で、ちょっとした生活費の足し、お小遣い稼ぎ、余暇や趣味を楽しむ目的で副収入を得るために若い内職さんが増えてきました。
2000年以降の現代ではインターネットが普及した影響でパソコン内職が主流になりつつあります。
インターネット上のデータの送信やデータの受け渡しのデジタルデータに関するお仕事では集荷や配達する必要がなくなるのでSOHOも同時に発展してきました。
近年では昔ながらの封筒のあて名書きのような手作業求人よりもパソコンでデータ入力など在宅ワーク内職の求人数が増えてきてます。
昔では内職さんは貧しいというマイナスイメージがありましたが、今では若い人から高齢者まで大人気のお仕事になってきてます。
それは終身雇用制度が終わった今の時代・自宅で手に職を求める人が増えてきているという事情もあります。
現在の内職の探し方としてはとにかく根気強く自分にあったお仕事を探す以外方法はありません。
仕事が来る時代から自分で仕事を求める時代になっているからです。
| 2015お役立ちナビランキング 結果発表 | 30日集計ReverseAccess | |
| 1位⇒家で出来る仕事ランキング | 2位⇒内職で100万円貯める方法 | 3位 ⇒データ入力無料登録 |
| 4位 ⇒昔ながらのハガキ内職 | 5位 ⇒40種類の内職実践記 | 6位 ⇒封筒と宛名書きの仕事 |

関連記事
